はじめに
ウォームスタンバイ(Warm standby), コールドスタンバイ(Cold standby), ホットスタンバイ(Hot standby)。
これらはどれも災害や万が一の事態などに備えて、システムを用意(スタンバイ)することを指します。
では、これらはどのような違いがあるのでしょうか。早速みていきましょー!!✨
用語説明〜最速で理解したい人のためのIT用語集より抜粋〜
ホットスタンバイ(Hot Standby)・・・本番用と全く同じ環境(サーバー, アプリケーション)にデータを常に同期し続け、障害時に本番機と瞬時に切り替えられるようにすること。
ウォームスタンバイ(Warm Standby)・・・普段は予備機(PC, サーバー)を最小限のリソースで起動させ、障害時に本番機と切り替えられるようにすること。
コールドスタンバイ(Cold Standby)・・・普段は電源を停止した予備機(PC, サーバー)を用意し、障害時に電源をつけリソースなどを用意した後、本番機と切り替えられるようにすること。
ホット / ウォーム / コールドスタンバイとは
本番用として実際に稼働しているシステムから、用意してある予備機への切り替えについて、
切り替え速度の点から、ホットスタンバイ > ウォームスタンバイ > コールドスタンバイというように分けられます。
「ホットスタンバイ」=本番用と全く同じシステムを予備機と常に同期させておき、障害時は本番機と瞬時に切り替えられるようにすること。最もコストはかかるが迅速に復旧でき、システムへの影響を最小限にできる。
「ウォームスタンバイ」=普段は本番より低スペックな予備機を起動させておき、障害時にリソースを追加した本番機と切り替えられるようにすること。データやアプリケーションは最後に更新したバージョン。
「コールドスタンバイ」=障害時用に予備機を用意しておき、障害時のみ電源を起動させ本番機と切り替えること。最もコストが低いが復旧までに時間がかかり、システムへの影響が大きい。
もう少し詳しくお伝えすると、
「ホットスタンバイ」は、本番機のリアルタイムデータが常に予備機と同期されており、瞬時(数秒から数分程度)に切り替えることができます。
少しでもダウンすることが許されない極めて重要なITシステムに対してのみ用いられ、他のスタンバイ方法に比べてコストが一番高くなります。
「ウォームスタンバイ」は、予備機の電源はONにしてあるものの起動させるリソースは最小限にとどめているので、本番機と切り替える際は少しパワーアップさせる必要があります。
ホットスタンバイに比べて時間がかかりますが、数分から数時間程度で予備機に切り替えることができます。
「コールドスタンバイ」は、予備機は用意してあるものの、電源は停止されており、障害が起きてはじめて本番用の環境をセッティングすることです。
データやアプリケーションのバージョンは必ずしも最新のものではなく、他のスタンバイ方法に比べて時間(数日から数週間)がかかりますが、一番安価で復旧条件が厳しくないシステムに用いられます。
<例文>
・あのシステムは会社の心臓となっているから、ホットスタンバイ装置を導入しよう。
・念のためにコールドスタンバイ用のPCを用意するか。
・社長、ホットスタンバイ装置を導入するのは予算的に厳しそうなので、ウォームスタンバイ装置は導入いたしましょう。
おわりに
いかがでしたでしょうか?これら全てのスタンバイ方法を理解することができましたでしょうか?
言葉は単発ではなく類語・対義語もセットで理解する方が記憶の定着と内容理解に良いと思うので、今回はまとめて紹介させていただきました。
この記事を通して「ウォームスタンバイ」「コールドスタンバイ」「ホットスタンバイ」に関する理解を深めていただけたら幸いです。
最後まで目を通していただきありがとうございました🙇♂️
参照元
.https://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/glossary/standby.html
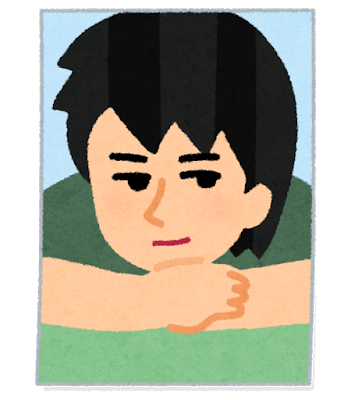







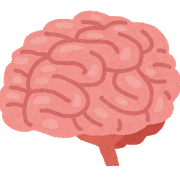
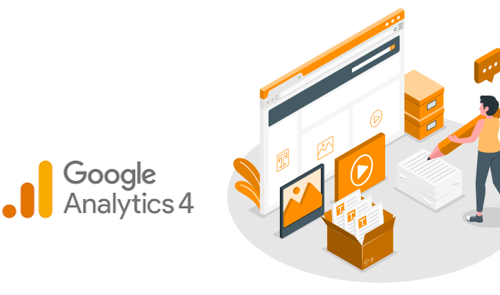
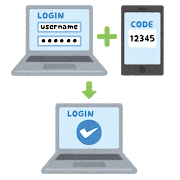
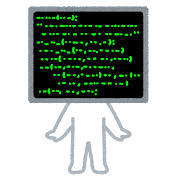

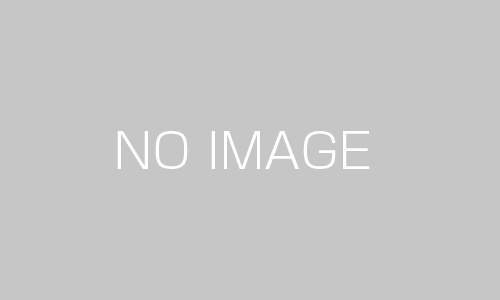
この記事へのコメントはありません。